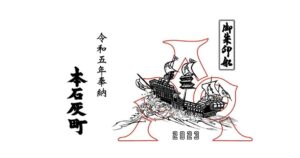令和7年11月2日、本石灰町の氏神様である大﨑神社の例大祭を執り行いました。
大﨑神社は、私たち本石灰町にとってかけがえのない氏神様です。
古くから町の守り神として鎮座され、町民の暮らしを見守り続けてこられました。
この例大祭は、一年に一度、氏子の皆様が集い、日頃の感謝をお伝えし、町の安寧と繁栄を祈る、本石灰町にとって最も大切な行事です。
今年も諏訪神社の吉村宮司様をはじめ、権禰宜様、巫女の皆様にお越しいただき、厳かに神事を執り行うことができました。
ここに、準備から当日、そして翌日の子供神輿まで、3日間にわたる行事の様子をご報告いたします。
10月18日(土)事前準備作業


例大祭に向けて、本石灰町青年部のメンバーが集まり、子供神輿の組み立てと神社の清掃を行いました。
神社を清め、神輿を組み立てる作業は、単なる準備作業ではありません。
若い世代が神社に関わり、先輩方から受け継いだ技術や心構えを学ぶ、大切な伝承の場となっています。
こうして町の伝統が、世代を超えて受け継がれていきます。
青年部の皆様の真摯な取り組みに、心から感謝申し上げます。
11月1日(金)大祭前日準備
役員一同で神社に集まり、翌日の例大祭に向けて最終的な清掃と準備を行いました。
境内を隅々まで清め、のぼり旗を立て、神社の社殿内の設えを整え、しめ縄を張り、例大祭の準備を丁寧に進めました。
一年に一度の大切な日を迎えるにあたり、役員一人ひとりが心を込めて準備に当たりました。
のぼり旗が秋風になびく様子は、例大祭を明日に控えた神社の凛とした雰囲気を一層高めます。
社殿内も清められ、神事を執り行う準備が整いました。
この準備の時間もまた、町の絆を深める大切なひとときとなっています。
11月2日(土)例大祭
神事(午前11時より)

秋晴れの穏やかな天候に恵まれた11月2日、午前11時より例大祭の神事を執り行いました。
諏訪神社より吉村宮司様、権禰宜様、巫女の皆様にお越しいただき、厳かに祝詞が奏上されました。
氏子の皆様も多数参列され、境内は清々しい空気に包まれました。
本石灰町の氏神様である大﨑神社に、日頃の感謝をお伝えし、町の安寧と発展、そして町民一人ひとりの健康と幸せを祈念いたしました。
神職の方々による丁寧な神事、参列者の真摯な祈りの姿勢は、まさに本石灰町の伝統と信仰の深さを物語るものでした。
直会

神事の後の直会では、諏訪神社の吉村宮司様より、大変貴重なお話を賜りました。
内容は、私たちがなぜこの例大祭を大切にしなければならないのか、その本質を深く理解する機会となりました。
「社会」という言葉の本質について
吉村宮司様は、「社会」という言葉の成り立ちについてお話しくださいました。
長崎出身の学者・福地源一郎が、英語の”society”を「社(やしろ)で会うこと」として説明したという歴史があります。
制度や仕組みより前に、まず人と人が会い、語り、関係が生まれる。
その瞬間こそが「社会」のはじまりです。
私たちが今日ここに集い、共に神様に祈りを捧げ、共に食事をする。
この行為そのものが「社会をつくる」営みなのだと教えていただきました。
長崎のまつりとコミュニティ
長崎くんちは諏訪神社の秋の例大祭であり、踊町が変わり、年番町が変わる中で、町ごとに「役」がまわる仕組みになっています。
町が役を受けたら、町で準備し、町で背負い、町で支え合う。
長崎は、この「社で会うこと」を続けてきた歴史を持つまちです。
まつりも、商いも、文化も、すべて”社で会うこと”から発展してきました。
この積み重ねこそが、長崎のコミュニティの強さの源なのです。
まつりは社会をつくる”実装の現場”
神社の祭を通して、人と人のコミュニティが形成されていきます。
社で会うことで、社会が立ち上がっていく。
まつりは「非日常」ではありません。
日常の関係と積み重ねが濃縮され、結晶化した場です。
だからこそ、まつりには地域の本質が可視化されます。
どこの町にも神社を中心とした祭りがあります。
祭りは「地域のコミュニティを形成するための、大切な装置」であり、地域が”社会になる”スイッチなのです。
大﨑神社の例大祭の意味
吉村宮司様のお言葉を、実際に大﨑神社という「社」の前で伺えたことは、参列者一同にとって、知識ではなく身体感覚として深く心に残る体験となりました。
私たちが毎年この例大祭を続けることは、単なる伝統行事を守ることではありません。
ここで会い、語り、支え合うことで、本石灰町という「社会」を育て続けているのです。
神社は、地域の”記憶”が宿る場所です。先人たちが守り続けてきたこの場所で、私たちもまた会い続けること。
それが、本石灰町のコミュニティを未来へ繋いでいく力になります。
11月3日(月・祝)子供神輿

例大祭の翌日、11月3日の文化の日、町内の子供たちと青年部、婦人部の役員の皆様が集まり、子供神輿を行いました。
大﨑神社の神様に神輿にお乗りいただき、本石灰町内を一周していただきました。
子供たちの元気な「おーみこし、おーみこし!」という掛け声が町内に響き渡り、それを支える大人たちの温かい眼差しと笑顔に包まれながら、神様に町内をご覧いただく貴重な時間となりました。
沿道では、多くの町民の皆様が手を振り、子供たちを応援してくださいました。
この光景は、まさに町全体で子供たちを、そして町の未来を育んでいる姿そのものです。
この子供神輿は、次世代に町の伝統を繋ぐ大切な行事です。
子供たちにとっては、本石灰町の一員としての誇りを育み、大﨑神社や町の文化を肌で感じる貴重な機会となっています。

ここでもまた、子供から大人まで、みんなが「社で会い」、共に汗を流し、共に笑い合う。
この積み重ねが、本石灰町の未来を明るく照らしていきます。
おわりに

大﨑神社の例大祭は、本石灰町にとって、何よりも大切なお祭りです。
この日、私たちは氏神様に感謝を捧げるだけでなく、町の仲間と顔を合わせ、共に時間を過ごします。
ここから、人と人とがつながり、ここから、町の文化が続いていきます。ここから、本石灰町という「社会」が生まれ続けていくのです。
吉村宮司様のお言葉にもあったように、「社で会うこと」で社会が生まれます。
だから神社が大事で、長崎のまつりが大事なのです。そして私たちにとって、大﨑神社の例大祭が何よりも大事なのです。
時代が変わっても、この祭りを続けていくこと。それは、先人たちから受け継いだ大切な責任であり、未来の本石灰町への贈り物でもあります。
これからも、人と会い、語り、支え合いながら、本石灰町のコミュニティを大切に育ててまいります。
そして子供たちに、この町の誇りと伝統を、しっかりと手渡していきたいと思います。
最後になりましたが、ご多用の中お越しいただきました諏訪神社の吉村宮司様、権禰宜様、巫女の皆様には、心より厚く御礼申し上げます。
また、準備から当日、翌日の子供神輿まで携わっていただきました青年部、婦人部、役員の皆様、そしてご参列いただきました氏子の皆様に、深く感謝申し上げます。
皆様のお力添えにより、今年も無事に例大祭を執り行うことができました。
来年もまた、この大切な祭りを共に祝えることを、心より楽しみにしております。
令和7年11月 本石灰町自治会